
[取材先]本坊酒造株式会社(鹿児島県)
明治5年(1872年)創業の本坊酒造は、『桜島』ブランドをはじめとする本格焼酎(焼酎乙類)のほか、ワイン、リキュールなどを製造する総合酒類メーカーです。1949年からはウイスキーづくりにも乗り出し、近年は海外でも評価を高めています。「ワールド・ウイスキー・アワード(WWA)2013」ではブレンデッド・モルト部門において世界最高賞を受賞し、国際的なウイスキーブランドとしても認知されるようになりました。しかし、そのウイスキーづくりは、苦難の連続でもありました。困難を乗り越え、世界に誇れるブランドをつくりあげてきた本坊 和人社長に、世界のマーケットに向けた事業戦略をオリックス鹿児島支店 北野 寛太が伺いました。
目次
事業休止の葛藤を超えて。ウイスキー製造への飽くなき情熱
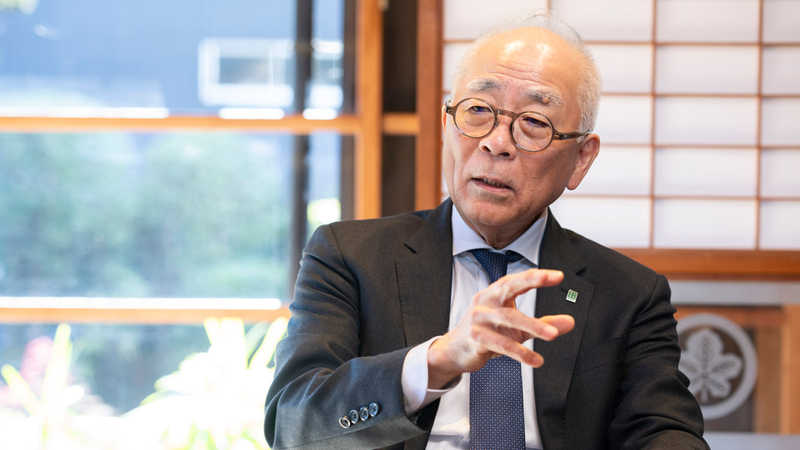
――はじめに本坊酒造の沿革について教えてください。老舗の蔵元として知られる御社は、なぜウイスキーづくりを始めたのでしょうか。
本坊氏:当社は明治維新から5年後の1872年に、綿花を加工する製綿業者として創業しました。その後、菜種油製造業や物品販売事業を経て、1909年に旧式焼酎(現在の本格焼酎)の製造を開始し、以来115年にわたって焼酎を中心に酒類をつくり続け、いまではワインやリキュールなどの製造も手掛ける総合酒類メーカーへと成長しました。
ウイスキーの製造免許を取得したのは、戦後間もない1949年、「これからは洋酒の時代が来る」と見越してのことです。自社で本格的なモルトウイスキーの原酒をつくるようになったのは1960年です。山梨工場(現・マルス山梨ワイナリー)新設の際に、アルコール精製技術の第一人者である岩井 喜一郎氏の設計によってポットスチル(ウイスキーの蒸留設備)が付設されました。その際、岩井氏は、日本人として初めて英国でウイスキーづくりを学んだ竹鶴 政孝氏の実習報告書、いわゆる「竹鶴ノート」を参考にしたとされています。岩井氏の製造指導によってウイスキーがつくられ、当社のブランドである『マルスウイスキー』が誕生します。いまなお多くのファンから愛され続ける国産ウイスキーですね。
――事業としては、最初から順調に成長したのでしょうか?
本坊氏:いえ、それこそ苦難の道です(笑)。私は1980年に本坊酒造に入社し、1982年に山梨工場へ赴任しました。そのとき、ポットスチルがホコリをかぶったまま放置されていたことを覚えています。その頃は完全にワイン製造が中心で、ウイスキーは鹿児島工場の小さなポットスチルでほそぼそとつくられているだけでした。
しかし、1980年代前半から「地ウイスキー」ブームが起こり始めます。それで当時の社長から「もう一度、ウイスキーをつくるぞ」と号令がかかり、私も携わって1985年に長野県上伊那郡宮田村に信州工場(現:マルス駒ヶ岳蒸溜所)を新設し、山梨工場の蒸留設備一式を移設して、大規模なウイスキーづくりを再開したのです。

――その後、いったんウイスキーの製造が中断したと聞きました。再開までの道のりはどのようなものだったのでしょうか。
本坊氏:地ウイスキーブームが落ち着いたあと、イギリスから輸入ウイスキーの税率引き下げを求められたことをきかっけに、アルコール度数によって決められていた「特級」「一級」「二級」の級別制度が1989年の酒税法改正で廃止されました。ウイスキーの酒税が一本化されたのです。
その影響で、当社の主力だった二級の『マルスウイスキー エクストラ』一升瓶の店頭価格が1630円から3200円へと格段に跳ね上がってしまったのです。当然売り上げは激減し、製造しても出荷の見込みがたたない。採算が取れなくなり、1992年に信州工場でのウイスキーの蒸留を休止しました。その流れは大手ウイスキーメーカーにも波及し、90年代はまさに「国産ウイスキー冬の時代」でした。出荷量は最盛期の最大で45分の1まで落ち込みました。社内では「ウイスキー事業から撤退し、製造免許を他社に譲り渡すべき」という意見もあったほどです。
潮目が変わったのは2008年頃です。ハイボールブームが起こり、株式会社ベンチャーウイスキーが、秩父に新しく蒸溜所を開設するなど、市場がにわかに活気づいたのです。それで当時の本坊 修社長(現・会長)に「蒸溜所にもう一度投資してほしい」と交渉したんですね。
ただ、老朽化した設備の補修には1億円の投資が必要で、社内でも議論が巻き起こりました。しかし、「先代の人たちが苦労して誇りを持ってやってきた事業を、私たちの代でつぶすわけにはいかない」と周囲を説得して、2009年にウイスキー事業再開のコンセンサスを社内で得ることができました。2011年2月に蒸留を再開、2016年には本坊家発祥の地でもあるここ津貫(南さつま市)に、第二蒸溜所を新設し、現在に至っています。
繊細ながらもふくよかな味わいの「駒ヶ岳」、南国らしい力強さの「津貫」

――では、あらためて本坊酒造が生み出すウイスキーの特徴を教えてください。
本坊氏:現在、駒ヶ岳(長野)と津貫(鹿児島)の蒸溜所でウイスキーを製造し、それぞれの蒸溜所の名を冠したシングルモルトを販売しています。『駒ヶ岳』は爽やかで繊細ながらも、ふくよかな味わい、かたや『津貫』は南国らしく、奥深さのある力強いフレーバーを持つことが特徴です。
特に津貫蒸溜所に関していえば、そもそも温暖な気候の土地はウイスキーづくりには向かないとされてきました。
世界で一番蒸溜所が多いスコットランドの平均気温は、冬は2〜6度、夏でも14〜19度と年間を通して寒冷です。本来ウイスキーの熟成には一年中ひんやりとした貯蔵庫が必要なのです。
そうした常識をくつがえし、九州最南端の鹿児島で気候というハンデを原料の栽培や原酒の製造方法、樽の選定など、ほかの要素で補いプラスに変える。津貫という土地の個性があふれた原酒を生み出している点も大きな特徴といえるでしょう。

また、津貫・駒ヶ岳でそれぞれ性格の異なる原酒を屋久島にある貯蔵庫で熟成させ、ブレンドした『MARS The Y.A.』も国内外から高い評価をいただいています。
通常、ウイスキー製造においては、蒸溜所と熟成させる貯蔵庫が同じ場所にあることが多いのですが、われわれはあえて貯蔵庫を別の場所に置くことで、独自の味わいを生み出すことを目指しています。
屋久島もまた平地部の平均気温が20度と言われる温暖な土地です。隆起サンゴ礁が広がる海岸からの潮風、世界自然遺産にも認定される豊かな自然と、原酒が生まれた土地とはまた異なる環境が、独自の熟成変化を生み出すわけです。
日本の自然を味方につけたウイスキーづくり、そういった他社とは一線を画すコンセプトを明確に打ち出すことが、世界に出ていくためのゲームチェンジに必要だと思っています。

――マーケットの軸足を海外へと移していく展開に注力されているように拝察しますが、やはり日本のウイスキー市場は縮小傾向にあるのでしょうか?
本坊氏:いえ、そんなことはありません。インバウンドによる売り上げも伸びていますし、日本のウイスキー市場は拡大傾向にあるといえるでしょうね。ジャパニーズウイスキーの世界的な人気も衰えてはいませんし、中国やアメリカをはじめ各国への輸出量も伸び続けています。しかし一方で、あまりにも高値で取引されるため、ジャパニーズウイスキーの買い控えも起こりつつあります。
そうした中で本坊酒造のウイスキーが海外の顧客にも選ばれていくためには、世界的なコンペティションで評価されること、リスペクトされるブランドを確立することだといえるでしょう。ワインと同様に、ウイスキーの評価はグローバルに基準が確立されていますから、その基準にかなう品質のウイスキーをつくることができれば、必ず市場で優位に立てると踏んでいます。
――なるほど。ウイスキーの市場自体には追い風が吹いている、と。
本坊氏:当社の売り上げ構成比でウイスキーが占める割合は、30%ほどにまで伸長しています。それはウイスキーの売り上げが伸びていることもありますが、主力の本格焼酎の出荷量が減少しているという事情もあります。価格競争やコモディティ化が進行し、収益化の難易度は上がっているといえます。
以前、私がフランスで仕事をしてみて驚いたのは、私たちよりずっと小規模な家族経営のワイナリーが、すごくいい決算を出していたことです。“価値を売る”という点については、欧米の生産家が圧倒的にたけている、と感じた出来事です。私たちも、いまようやくウイスキーで、そうした収益性の高いビジネスモデルを確立しつつあるように感じています。
もちろん、祖業である焼酎製造においてもゲームチェンジに挑戦しているところです。例えば『茜風43』という焼酎は、特許技術である「すりおろし生芋製法」で製造しています。
これは、洗浄した新鮮なさつま芋を蒸さずに、生芋のまま酒母と一緒にすりおろして発酵させ、蒸留する時に初めて加熱する製法です。一般的な芋焼酎の原料芋を蒸す加熱工程では、甘く香ばしい良い香りの湯気が蒸溜所内にたちこめますが、この湯気や香りが製品に生かされることはこれまでありませんでした。この「すりおろし生芋製法」を採用することで、初めての味わいが生まれたと自負しています。
700mlで5940円と一般的な焼酎の3~4倍ほどの高価格帯商品です。しかし、そのうまさが評価され、通のあいだでジワジワと評判を呼び、スピリッツの世界的なコンペティションでも最高金賞を受賞できました。こうした「価値を持った」製品をいかに生み出していくか。そこを試行錯誤して、業界に新しい風を吹き込んでいきたいと考えています。

土地の特色を生かした、本坊酒造らしいウイスキーづくり
それでは、実際に本坊酒造のウイスキー製造をリードしている社員の方は、日々どのような思いを持って仕事に取り組まれているのでしょうか。入社11年目、同社でチーフディスティリングマネージャー兼ブレンダーを務める、草野 辰朗さんにお話を聞きました。

――はじめに、草野さんのお仕事について教えてください。
草野氏:ウイスキーの状態や香味を見極めて管理すること、そして熟成を終えたお酒の配合を考えて製品にすることが主な仕事です。ウイスキーは、麦芽を原料として1週間ほどかけてつくった原酒を樽に入れ、最短でも3年、長いもので30年を超える熟成を経て出来上がります。
樽は、バーボンやシェリー酒の熟成に使われていたものを使うことが多く、以前入っていたお酒の種類によって樽香が変わり、熟成の香味も変化します。もちろん、樽に使用されている木材の樹種によっても違いますし、新品の樽だと、樽香が強すぎてしまう場合もあります。ここマルス津貫蒸溜所には、4000丁ほどの樽があり、最も古いのは設立時の2016年に樽詰めされたものです。
年に一回、熟成中のウイスキー全ての樽でチェックを行います。樽単体(シングルカスク)でリリースできるもの、ブレンドのキーになるもの、まだまだ熟成が必要なものなどを見極める作業です。品質を決定づける重要な工程なのでプレッシャーもありますが、自分の舌を信じて判断をくだしています。

――津貫蒸留所ならではのウイスキーづくりのこだわり。それは何でしょうか?
草野氏:先ほど社長からもお伝えした通り、鹿児島という温暖な気候の土地でウイスキーづくりにチャレンジしていること自体が、独自の味わいにつながっているように思います。
また最近では、地元産の大麦麦芽(ローカルバーレイ)を使ったウイスキーの製造にチャレンジしています。通常、麦芽は海外産を使いますが、地元産を使ったウイスキーには、なんといってもロマンがあると思っていますね。他にも、収量の少ない古代種の大麦を使うことにも挑戦していて、穀物本来の力強さや植物的な香りなど、個性の際立ったウイスキーをつくることができています。
ウイスキーはいわば、「多様性を楽しむ」お酒です。これからもさまざまな個性を持った新しいウイスキーづくりに挑戦しながら、国内・国外を問わず評価される品質に仕上げていきたいですね。「どうだ、日本のウイスキーはすごいだろう!」と海外にも胸を張って勧められる1本を生み出していきたいですね。
舌の肥えた世界のウイスキーファンに認められる品質を
再び、本坊社長にお話を伺います。

――最後に、今後のビジョンについてお伺いさせてください。
本坊氏:これまで、シングルモルトの『駒ヶ岳』『津貫』については、製造年を明記したリミテッドエディションとして製造・販売を行ってきました。しかし近々、年数表記をしないノンエイジに切り替える予定でいます。『駒ヶ岳』『津貫』を通年で、安定的に供給していける体制が整いつつある、ということです。ノンエイジの製造が実現し、常にお客さまのお手元に届けられることができるようになれば、私たちのブランドもこれまで以上に知名度を上げていくことができるでしょう。また、過去のリミテッドエディションの価値も上がっていくのではないでしょうか。

われわれは大手メーカーさんのように大規模なプロモーションや広告宣伝はできません。コアなウイスキーファンにも認められる、高品質な製品を地道に、プライドを持ってつくっていくこと。それが1番のPRになるのではないかと思います。
今の時代は、SNSの投稿をキッカケに国境を越えてヒット商品が生まれることも珍しくありません。ウイスキーファンが誰かに勧めたくなるような品質のウイスキーをつくり続けること、私たちの魂を込めながらつくり続けていくこと。それが、勝機につながっていくのではないでしょうか。
これまで、あまりウイスキーを飲んでいない若い方々にも本坊酒造のウイスキーを飲んでもらえるよう、頑張っていきたいですね。ご期待ください。
<取材を終えて>
オリックス株式会社 鹿児島支店 北野 寛太

本坊社長のお話を伺って、総合酒類メーカーとしてさまざまな分野にチャレンジしている裏には、先人たちから受け継いだお酒づくりへの情熱があることがわかりました。これからも紡がれてきた思いを次世代につないでいくためのお手伝いを、オリックスとしてお力添えさせていただきたいと思いました。ぜひ皆さんも、本坊酒造さんのお酒を一度飲んでみてほしいと思います。
本記事で紹介した商品はこちらのサイトで購入可能です
企業概要※ 公開日時点
| 社名 | 本坊酒造株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 鹿児島県鹿児島市南栄3丁目27番地 |
| 設立 | 1955年10月1日 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 本坊 和人 |
| 従業員数 | 210名 [パート・アルバイト含] (2023年3月現在) |
| 事業概要 | 酒類の製造販売、山林農園経営、観光事業、不動産売買賃貸借 |





