お知らせ
企業情報
2021/10/01
SDGsの取り組み
オリックスグループは、事業活動を通じて社会に貢献するという考えのもと常に新しい価値を創造し、社会から必要とされる存在であり続けることを目指しています。
私たちは、国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、環境・社会・経済のサステナビリティにおける重要な課題解決に貢献し、持続可能な社会の実現に向けたサービス展開をしています。

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。
私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。
【5】ジェンダー平等を実現しよう

年齢や性別に関係なく活躍できる職場環境づくりを行っています。社員のキャリア形成、ワークライフバランスを実現するため、男女共に、出産・育児・介護など、ライフステージに合わせた働き方ができる環境を構築します。
詳細はこちら
【7】エネルギーをみんなに そしてクリーンに
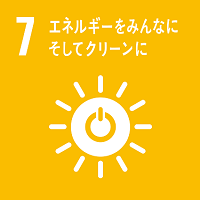
弊社は太陽光電源の高効率な運用を通して、再生可能エネルギー電源の普及促進を目指し、市場の発展と日本のエネルギーミックスに貢献します。
詳細はこちら
【8】働きがいも 経済成長も
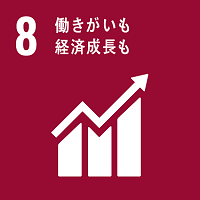
弊社では、社員がそれぞれの志向とライフスタイルに応じて活躍できるよう、働き方を支援する制度を整えています。これまでプライベートとの両立をサポートする福利厚生のほか、仕事の成長を後押しする資格取得支援などユニークな施策を導入してきました。今後も既存の制度にとらわれず、環境の変化などに柔軟に対応できる組織形成および企業成長に努めます。
詳細はこちら
【9】産業と技術革新の基盤をつくろう

弊社はカーボンニュートラルの実現に向けて、AIやブロックチェーンなどデジタル技術を活用し、人とテクノロジーで太陽光発電所の最大効率化を図る取り組みを進めています。さらにデータマネジメントによって不確定要素を日々の天候に限定し、明日の発電量を予測・コントロールできる社会の実現を目指しています。デジタル化で発電量を予測・コントロールし、既存の電気インフラの負担を軽減させることで、社会コストの低減に寄与しています。
詳細はこちら
【12】つくる責任 つかう責任

カーボンニュートラルの実現に向けたエネルギーミックス転換のため、全世界で普及が加速しつつあるのが太陽光発電所です。日本も例外ではなく今日も新しい発電所の開発、建設が進んでいますが「新しい発電所をつくること」は自然破壊にも繋がりかねません。国内の主要太陽光発電事業者の責務を全うすべく、再生可能エネルギー電源普及促進のために設立された弊社は、再生可能エネルギーの電源比率向上を実現する上で「新しい発電所をつくること」と同等の価値がある「既設発電所の効率を高めること」で持続可能な社会の実現に貢献しています。
詳細はこちら
【13】気候変動に具体的な対策を

温室効果ガスの削減は、持続可能な社会の実現に向けて、今や世界共通で取り組まなければならないミッションです。しかし、再生可能エネルギー先進国とされる他の国と比較し、日本においては発電所の運営管理水準が引き上がっていません。多くの発電所で、想定を上回る速度でプラントが劣化している事例が確認されていますが、発電事業者の多くは、メンテナンス費用をコストとして捉えているため、エネルギーロスをしているという課題があります。最適なO&Mは発電量を最大化し、さらにプラントを長寿命化させることで部材交換費なども極小化できるため、売電収益の大幅な改善に繋がります。弊社は予防保全型のO&Mで発電事業者の売電収益を改善し、O&M費の実質0円を目指し、発電事業者の事業管理費の低減とカーボンニュートラルの実現を加速させます。
詳細はこちら
【17】パートナーシップで目標を達成しよう

弊社は多様な組織・企業とパートナーシップを締結し、国内外を問わずさまざまな状況に対応できるビジネスパートナーさまとのネットワークを構築しています。また、業界の発展のため「太陽光発電所のアセットマネジメント」を共通テーマに、次世代電力システムに関する国際商談展にも多くの企業と共同出展し、発電所の期中管理におけるトータルソリューションをご提案するなど、最新の技術・情報を共有、発信することで持続可能な社会の実現を目指します。
ビジネスパートナーさまへ
国際商談展についてはこちら
私たちは、国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、環境・社会・経済のサステナビリティにおける重要な課題解決に貢献し、持続可能な社会の実現に向けたサービス展開をしています。
SDGsとは

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。
私たちの取り組み
私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。
【5】ジェンダー平等を実現しよう
年齢や性別に関係なく活躍できる職場環境づくりを行っています。社員のキャリア形成、ワークライフバランスを実現するため、男女共に、出産・育児・介護など、ライフステージに合わせた働き方ができる環境を構築します。
詳細はこちら
【7】エネルギーをみんなに そしてクリーンに
弊社は太陽光電源の高効率な運用を通して、再生可能エネルギー電源の普及促進を目指し、市場の発展と日本のエネルギーミックスに貢献します。
詳細はこちら
【8】働きがいも 経済成長も
弊社では、社員がそれぞれの志向とライフスタイルに応じて活躍できるよう、働き方を支援する制度を整えています。これまでプライベートとの両立をサポートする福利厚生のほか、仕事の成長を後押しする資格取得支援などユニークな施策を導入してきました。今後も既存の制度にとらわれず、環境の変化などに柔軟に対応できる組織形成および企業成長に努めます。
詳細はこちら
【9】産業と技術革新の基盤をつくろう
弊社はカーボンニュートラルの実現に向けて、AIやブロックチェーンなどデジタル技術を活用し、人とテクノロジーで太陽光発電所の最大効率化を図る取り組みを進めています。さらにデータマネジメントによって不確定要素を日々の天候に限定し、明日の発電量を予測・コントロールできる社会の実現を目指しています。デジタル化で発電量を予測・コントロールし、既存の電気インフラの負担を軽減させることで、社会コストの低減に寄与しています。
詳細はこちら
【12】つくる責任 つかう責任
カーボンニュートラルの実現に向けたエネルギーミックス転換のため、全世界で普及が加速しつつあるのが太陽光発電所です。日本も例外ではなく今日も新しい発電所の開発、建設が進んでいますが「新しい発電所をつくること」は自然破壊にも繋がりかねません。国内の主要太陽光発電事業者の責務を全うすべく、再生可能エネルギー電源普及促進のために設立された弊社は、再生可能エネルギーの電源比率向上を実現する上で「新しい発電所をつくること」と同等の価値がある「既設発電所の効率を高めること」で持続可能な社会の実現に貢献しています。
詳細はこちら
【13】気候変動に具体的な対策を
温室効果ガスの削減は、持続可能な社会の実現に向けて、今や世界共通で取り組まなければならないミッションです。しかし、再生可能エネルギー先進国とされる他の国と比較し、日本においては発電所の運営管理水準が引き上がっていません。多くの発電所で、想定を上回る速度でプラントが劣化している事例が確認されていますが、発電事業者の多くは、メンテナンス費用をコストとして捉えているため、エネルギーロスをしているという課題があります。最適なO&Mは発電量を最大化し、さらにプラントを長寿命化させることで部材交換費なども極小化できるため、売電収益の大幅な改善に繋がります。弊社は予防保全型のO&Mで発電事業者の売電収益を改善し、O&M費の実質0円を目指し、発電事業者の事業管理費の低減とカーボンニュートラルの実現を加速させます。
詳細はこちら
【17】パートナーシップで目標を達成しよう
弊社は多様な組織・企業とパートナーシップを締結し、国内外を問わずさまざまな状況に対応できるビジネスパートナーさまとのネットワークを構築しています。また、業界の発展のため「太陽光発電所のアセットマネジメント」を共通テーマに、次世代電力システムに関する国際商談展にも多くの企業と共同出展し、発電所の期中管理におけるトータルソリューションをご提案するなど、最新の技術・情報を共有、発信することで持続可能な社会の実現を目指します。
ビジネスパートナーさまへ
国際商談展についてはこちら