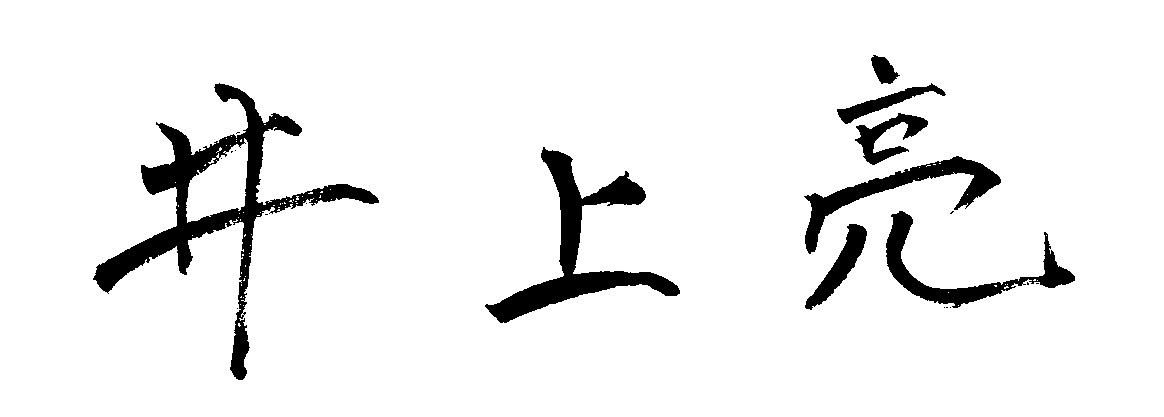CEOメッセージ

失敗こそが成功のカギ。
1つの失敗には100の成功より多くの学びがつまっています。
環境変化は成長を続ける「糧」
2025年3月期は、当初目標(純利益3,900億円)は未達となりましたが、連結当期純利益は3,516億円となり、過去最高益を2期連続で更新しました。2026年3月期は不透明な外部環境が続いていくものと考えていますが、オリックスとして、さらに高い水準を目指して努力していく所存です。
新たな中期目標を発表させていただきましたが、これはグループすべてのお客さま、取引先、従業員、投資家、株主の幅広いご支持があって実現できる目標であり、引き続き、皆さまのご支援やご信頼を賜りたく、お願い申し上げます。
当社へのさらなるご理解を深めていただくために、当該統合報告書を作成しましたので、皆さまにおかれまして、ご参照いただければ幸甚と存じます。
オリックスは創業以来、約60年にわたり、ポートフォリオの入れ替えを機動的に行うことで、変化する経済環境の中でも成長し続ける力を培ってきました。創業当初のリース業を起点として、国内外のさまざまな「金融」領域で、ノウハウと経験を積み重ねてきました。これら多岐にわたる経験を生かし、自動車、電子機器、不動産、空港、再生可能エネルギー、輸送機器、アセットマネジメントなど多くの「事業」領域において展開することにより、国内外における新たな資産の構築を、機動的かつ積極的に実行しています。多様化され、分散されたポートフォリオを、マーケット動向を意識しながら回転させることで、オリックスという「独自性」を維持する企業体を構築できたと理解しています。
世界経済は不確実性の高まりと構造的な変化が続いています。地政学リスクの高まり、貿易摩擦の激化、インフレの継続、各国の金融政策動向の不透明さなど、世界の資本市場においてボラティリティが極めて高まっていると考えています。企業経営における判断基準はますます複雑化していますが、こうした環境変化において慎重かつ大胆な意思決定を可能とすることが、オリックスの成長を続ける「糧」だと考えています。
失敗の経験こそ成長のカギ
オリックスは現在、世界約30の国・地域で事業展開し、グループ従業員は約34,000名です。2023年11月に導入した「ORIX Group Purpose & Culture」のもと、グループの一体感を高めながら、お客さまのニーズに応え、多くの国や地域における取引先との商慣行を遵守し、現地の金融市場動向を見極めながら、さまざまな案件を的確に決裁していくことが、トップマネジメントの重要な責務です。
徹底したデューデリジェンスやドキュメンテーションに注力しながら、スピード感を持って経営判断していくことが重要です。オリックスにとって、日頃から変化をチャンスと捉えて、率先して新たな取り組みに挑むマインドを維持することが不可欠であると考えています。
オリックスの成長の歴史は、失敗の経験をノウハウとして個人ではなく組織として吸収し、次のディールにつなげてきたことです。現在、コアセグメントとなっている船舶事業、航空機事業は、過去において多額の損失計上を余儀なくされた経験を持ちます。減損、事業撤退による手仕舞いをせずに、それぞれの事業の特性を把握し、過去の失敗の経験を糧として事業を継続した結果、収益性の高いセグメントに成長した実績があります。
1977年に、船舶貸渡許可取得のために設立したペルサス・シッピング(現オリックス・マリタイム)、1991年に、航空機登録のために設立したORIX Aviation Systems(OAS)は、結果的に事故処理等の対応に終始しましたが、運航、保守管理、マーケットにおける対応策など、多くのノウハウの蓄積ができたことが大きな成果物となりました。船舶事業分野においては、今年度までに、三徳船舶株式会社、ソメック株式会社がグループに参加、船舶業界において特異な地位を築くことができたと言えます。航空機事業分野においては、1991年に倒産した航空会社から74機(発注権24機・オプション50機)を購入したことから航空機リース事業を開始しましたが、湾岸戦争、多くの航空会社の倒産、所有エンジンの設計上の問題発覚、同時多発テロなど、多くの苦い経験をしました。しかしながら、この経験によりノウハウの蓄積が可能となり、現在は、世界3番目の規模を誇るAvolon社の30%の株式を保有し、OASと合わせて、航空機リース事業におけるPrimary/Secondary分野において確固たる地位を確立するに至っています。
オリックスでは、失敗の経験こそ成長のカギになり得ると考えています。1つの失敗には100の成功よりも遥かに多くの学びが詰まっています。危機を乗り越えた対策がノウハウとなり、次の挑戦で生かすことにつながり、また、変化の大きい環境で、成長のチャンスと捉えて果敢に挑むことができます。減点主義ではなく加点主義で挽回の機会を掴むことがオリックスの強みであると考えています。
2008年頃発生した世界的な金融危機が、オリックスグループに、リスク管理の重要性を学ぶ機会を与えてくれたと認識しています。以降、十数年間において、大幅な業績回復と企業価値向上に繋がったと考えています。
オリックスは、バブル崩壊、リーマンショックを起因として、長引く円のゼロ金利政策により、収益性を維持することが困難となっていく金融事業から、不動産などの事業に積極的に資本配分をしましたが、国内の不動産取引の急激な縮小や、世界的な金融市場の急激な収縮に直面しました。当時、資金調達を短期コマーシャル・ペーパーに依存していたオリックスは、銀行借入などの負債項目に対して大幅な圧縮を迫られたことから、株価が大きく低迷する危機を経験しました。その経験から、オリックスはグループの事業の多角化を進めると同時に、ポートフォリオのリスク分散、入れ替えの推進、財務基盤健全化に注力しました。資本金を多角化した事業に分散すること、環境変化に対して臨機応変に対応できる体制を構築できたことで、グループの持続的な利益成長が可能となりました。
加えて、企業ガバナンス強化の取り組み、リスク管理の高度化を最重要テーマとして、定量的にグループの市場リスク、信用リスク、オペレーションリスク、流動性リスクの認識、分析を可能とする「リスクダッシュボード」を構築しました。このシステムにより、堅実な財務規律の実践を含め、事業部門の迅速な案件の分析・評価、管理部門のタイムリーな関与が可能となり、経営の意思決定に活用できる状態となりました。
迅速な意思決定と権限委譲により生き残る

中期経営計画の経営目標として、2028年3月期においてのROE11%、A格の国際信用格付、2035年3月期においてのROE15%、純利益1兆円を掲げています。その達成のためには、悪戯に総資産を増やすことは得策とは言えません。また、財務の健全性と収益性を確保するためにもA格の国際信用格付の維持は重要な経営テーマであると考えています。
オリックスの経営戦略として、キャピタルリサイクリングの推進を掲げています。子会社を含めすべてのポートフォリオについて、日頃から投資先価値を高める経営を行いながら成長性を見極めた上で、常に流動性の確保、適切なタイミングを模索する必要があります。
投資案件は、実行したその日から陳腐化するリスクがあります。どれほど魅力的に見える案件でも、マーケットの変動により企業価値は変わります。環境が悪化してから対策を考えるのでは手遅れとなるため、日々のモニタリングが重要となります。リターンの最大化とリスクの最小化を両立するためにも、キャピタルリサイクリングを行動指針とすることが確固たる経営方針となることを認識すべきと考えています。変化する市場で、ポートフォリオの資本配分を常に最適化する上では、客観的な分析と冷静な判断が不可欠です。ROAやROEが相対的に低い案件は、積極的にキャピタルリサイクリングの対象となることを前提に、売却時期の判断を的確に行うための仕組みを構築しています。
オリックスの事業と組織は格段に規模が大きくなり、複雑なクロスボーダー取り組み、国内外のM&A案件など、多様な事業への投資機会が増加しています。その対応のためにも多様な人材の確保と、その人材が活躍できるグループ一体としての環境づくりが、これまで以上に重要になっています。すぐれた人材を獲得し、すべての役職員にオリックスの企業文化を理解してもらい、それぞれの分野でプロフェッショナルとして成長し、グローバルに活躍してもらうためにも、グループの人的資本を拡充することが、経営の最重要課題です。
海外におけるビジネスの現場では、曖昧さを排した明快なコミュニケーションと、交渉の場における迅速な意思決定が重要と考えています。各国で採用した人材に責任を持たせること、そして、その人材に権限を委譲することが、グローバルに事業を展開・拡大させるためにも、グループとして重要なテーマだと認識しています。それぞれの現場において、個々人に責任と権限を与えることは、自立を重視するオリックスの人的資本経営の基本であると考えています。人材獲得や育成と同時に、グローバルな競争力向上に資するための報酬制度を見直すことも必要です。グループのさまざまな事業や地域ごとに、それぞれの役割や成果に応じて、マーケット水準に沿って処遇される報酬制度を構築することは、人的資本経営に不可欠です。
このような改革には一定の時間が必要となりますが、グローバルで生き残るためには喫緊の課題であり、早急な対応が求められていると認識しています。
一体感とスピードを緩めず未来を切り拓く
1月1日付で髙橋 英丈氏が代表執行役社長・グループCOOに就任しました。経営判断に関わる小職の権限を一部委譲し、髙橋新社長はCOOとして業務執行の重要な意思決定に関する責任を担います。CEOおよびCOOは経営の方向性を共有することが重要であり、グループの一体感や意思決定のスピードを緩めることはありません。投資判断における評価基準、将来の市場見通し、出口戦略、ROEや信用格付に関する方針、ESGといった多角的な経営の方向性に変更はありません。
オリックスは大株主を持たず、自主独立路線で進路を開拓してきました。自立心を持って行動する役職員の集合体として、オリックスの未来を見据えることは、今後も維持すべきオリックスの基本的なカルチャーだと思っています。事業部門からも、管理部門からも、それぞれが提案してきた案件や意見は全体最適と一致するとは限りません。個々の提案や意見は尊重しつつも決して誘導されず、中長期に全社的な立場で最適な判断を下すことが経営の責任です。そうした実績の積み重ねが、経営全体の質を高め、企業としての信頼や評価を高めていきます。
オリックスをして、エクセレントカンパニーと認められる評価を勝ち取る努力を怠ることなく、将来を見据えていくことが大切だと考えています。
今年5月に2035年に向けた長期ビジョンと2028年までの中期経営計画を発表し、グローバル経営会議を通じて世界中のマネジメントとも共有しました。今後、資本効率の向上、ポートフォリオマネジメントの強化、新規事業の創出に一層注力いたします。また、人的資本経営を推進し、サステナブルな社会への貢献を目指して、皆さまのご期待にお応えしていきたいとの姿勢は不変です。
皆さまのご支援とご信頼をどうぞよろしくお願い申し上げます。

コラム:グローバル経営会議の開催
コロナ禍後初めてとなるグローバル経営会議を開催しました。国内外約120名のマネジメントが一堂に会して、オリックスグループの長期ビジョンや中期経営計画を議論し、成長分野や協業の可能性について、率直かつ前向きな意見を交わしました。
CEOとCOOが率先してグループが進むべき方向をプレゼンし、「一体感のあるグローバルチーム」としての意識がより一層強まり、結果、オリックスが次のステージへと踏み出す上で、大きな意味を持つ機会となりました。これからの成長に向けて、国・地域や事業の枠を超えた連携を通じて、企業価値向上への挑戦を続けてまいります。